全国の吹奏楽部員を応援するこのブログ「吹ブロ!」を書いている、夢緒と申します。
少しでも多くの方に、吹奏楽を知って欲しい
すでに継続中の方には、より楽しく吹奏楽を続けてもらいたい
という思いで、このブログを書いています。

吹奏楽部に入ってすぐは、担当楽器にも慣れていないし、話したことのない先輩達に囲まれて、慣れない環境で分からないことだらけで不安ですよね。
そんな環境の中、新入部員のみなさんたちをさらに混乱させる「特別なルール」があります。
それは、「ドイツ音名」という音の読み方です。
ドイツ音名とは、例えば「べー」「ツェー」というような、吹奏楽で登場するすべての楽器に共通する譜面の読み方のことです。
実はこの、【すべての楽器に共通する】という部分がポイント。
ドレミで読んでしまうと困ることが起きるので、わざわざドイツ音名を使っています。
この記事を書いている私が吹奏楽部でドイツ音名を知ったのは、小学校4年生でした。
ある日の部活中。先輩たちの合奏を4年生全員で見学した時のことです。
指揮者である先生が
「全員で『べー』を出して。」
と指示すると、部員全員で同じ音が出され、チューニングが行われたわけですが…
私たち4年生にとって、チューニングの内容なんかよりも、何よりもまず、
「『べー』って何!?」
という疑問が、ずっと頭の中をグルグルと回っている状態でした。
こんな感じで、吹奏楽部に入りたての頃、
「『べー』じゃなくて『ド』じゃだめなの?」
「なぜ聞き慣れた『ドレミ』が出てこないんだろう…」
という疑問を抱いたことのある人は、意外に多いのではないでしょうか。
そして、ドイツ音名には吹奏楽部員の多くが苦労させられるにもかかわらず、意外にも、部活での練習中にきちんと学ぶ機会がないまま、日々過ごしていく中でなんとなく覚えていくことが多い印象です。
この記事では、吹奏楽部員が入部当初に苦労させられる「ドイツ音名」について、初心者向けに解説します。
吹奏楽部でドレミではなくドイツ音名を使う理由や、ドイツ音名を理解するのに欠かせない「楽器ごとの『ド』の音の違い」について(いわゆる「○○管」というやつです)が主な内容です。
ドイツ音名についてこれまできちんと学ぶ機会がなかった方や、いまいち理解できていないまま過ごしている部員のみなさん。また、入部して間もなくドイツ音名がまったく分からない方。そんな方に読んでいただき、少しでも日頃の練習に役立てば嬉しいです。
吹奏楽部でドレミではなく、ドイツ音名を使う理由とは?

「ドイツ音名」と聞くと、なんとなくかっこいい印象を持ちませんか?
私が吹奏楽部に入部した当初は、先輩たちや顧問の先生がドイツ音名をバンバン使っている様子を見て、本気で、
「特に意味はないけど、格好つけたいから使っているだけなんじゃないの~?」
くらいに考えていました(先生、先輩たち、本当にごめんなさい^^;)
もちろん、かっこいいから使っているわけではなく、使うのにはきちんとした理由があります。
ドイツ音名を使う理由は
吹奏楽で登場する楽器は、それぞれ、楽譜上の「ド」の音が異なるから
です。
「ド」の音が異なるって、どういうこと?と思いますよね。
具体的な例で紹介します。
例えば、フルート奏者、クラリネット奏者、サックス奏者の3人が同時に、楽譜上に書かれている「ド」の音を出したとします。
そうすると、全員が楽譜上のドの音を出しているのに、3人ともバラバラの音が出てしまうのです。
ですが、ここでドイツ音名を使って、
「『べー』の音を出してください」
と言って合奏すれば、3人とも同じ音が出せるのです。
そうすることで、全体で音合わせ(チューニング)などをスムーズに行うことができます。
そう、ドイツ音名は、実はとても便利なものなのですよ^^
吹奏楽部内における、楽譜上の共通語のようなものなのです。
「○○管」って何の違い?あなたの担当楽器はどのグループか、確認しよう!

楽譜上で「ド」と書いてあっても、その音は楽器ごとでバラバラなので、共通語としてドイツ音名を使うのだと説明しましたが、吹奏楽に登場する楽器すべてがバラバラなわけではありません。
ここで、吹奏楽に登場する楽器を4つにグループ分けしていきます。
あなたの担当楽器がどのグループに入っているか、見てみてくださいね。
①B♭管(ベーかん)…クラリネット、ソプラノサックス、テナーサックス、トランペット、トロンボーン、ユーフォニアム、チューバ
②F管(エフかん)…ホルン
③E♭管(エスかん)…アルトサックス
④C管(ツェーかん)…フルート、ピッコロ、オーボエ、ファゴット、ピアノ、木琴などの鍵盤楽器
これらは、譜面上の「ド」の音が共通しているグループで分けています。
自分の担当楽器がどのグループに入っているか、確認できましたか?
次からは4つにグループ分けしたものを1グループずつ、詳しく解説していきますので、自分の担当楽器が該当するところを読んでみてくださいね。
※ご注意※
今回の種類分けは、その楽器でもっとも多い種類で分けており、初心者向けの楽器によくあるもののみ紹介しています。あらかじめご了承ください。
例えば、クラリネットであれば、吹奏楽部で使用する学校用楽器や楽器初心者用のものの多くはB♭管ですので、今回B♭管で分類しています。
ですが、吹奏楽ではなくオーケストラ用のものや上級者向け・プロ用などはA管(アーカン)という珍しいものなどもあります。
クラリネット=すべてB♭管というわけではなく、今回4つに種類分けした「○○管」も、細かく分けるとさらに種類がありますが、今回は紹介を省かせていただいています。
①B♭管(ベーかん)
【移調楽器】ドを吹くと、B♭(ベー)が出ます。【ド=B♭】
②B♭管(ベーかん)のグループは、楽譜上のド=ドイツ音名「B♭(ベー)」となる楽器です。
B♭管の楽器で、譜面上の
【ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド】
と吹いた場合、
【B♭(ベー)・C(ツェー)・D(デー)・E♭(エス)・F(エフ)・G(ゲー)・A(アー)・B♭(ベー)】
という音が出ることになります。
グループ分けで見ていただいた通り、吹奏楽で登場する楽器の半数以上はB♭管のグループに入りますので、多くの楽器がこのグループに該当しています。
吹奏楽ではこのグループが一番多い。チューニングがB♭なのもこれが理由。
ここで、吹奏楽部の日々の練習で欠かせない「チューニング」の話をします。
吹奏楽部では、チューニングの時にB♭(ベー)の音で合わせることが多いと思いますが、実は、その理由もここにあります。
吹奏楽部で使う多くの楽器がB♭管である。
→つまり、ド=B♭である楽器が多い。
→それなら、多くの楽器の基準音(ド)であるB♭で音を合わせよう。
というわけですね。
担当楽器がB♭管の方は、チューニングで
「B♭(ベー)の音を出して」と言われたら「ド」の音を出せばOK
ということになりますので、比較的覚えやすいのではないかなと思います。
※まれに、学校や楽団によっては、チューニング時にB♭以外の音を使っているところもあるかもしれません。また、吹奏楽ではなくオーケストラの場合、B♭以外の音でチューニングをする可能性が高いです。所属している楽団・部のルールを、先輩や先生に聞いてみてくださいね。
②F管(エフかん)
【移調楽器】ドを吹くと、F(エフ)が出ます。【ファ=B♭】
②F管(エフかん)のグループは、楽譜上のド=ドイツ音名「F(エフ)」となる楽器群です。
F管の楽器で、譜面上の
【ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド】
と吹いた場合、
【F(エフ)・G(ゲー)・A(アー)・B♭(ベー)・C(ツェー)・D(デー)・E(エー)・F(エフ)】
という音が出ることになります。
F管楽器のみなさんは、チューニングの時に
「B♭(ベー)の音を出して」と言われたら「ファ」の音を出せばOK
というふうに覚えておきましょう。
③E♭管(エスかん)
【移調楽器】ドを吹くと、E♭(エス)が出ます。【ソ=B♭】
③E♭(エスかん)のグループは、楽譜上のド=ドイツ音名「E♭(エス)」となる楽器群です。
E♭管の楽器で、譜面上の
【ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド】
と吹いた場合、
【E♭(エス)・F(エフ)・G(ゲー)・A♭(アス)・B♭(ベー)・C(ツェー)・D(デー)・E♭(エス)】
という音が出ることになります。
F管楽器のみなさんは、チューニングの時に
「B♭(ベー)の音を出して」と言われたら「ソ」の音を出せばOK
というふうに覚えておきましょう。
④C管(ツェーかん)
ドを吹くと、C(ツェー)が出ます。【シ♭=B♭】※Cは実は…
④C管(ツェーかん)のグループは、楽譜上のド=ドイツ音名「C(ツェー)」となる楽器群です。
C管の楽器で、譜面上の
【ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド】
と吹いた場合、
【C(ツェー)・D(デー)・E(エー)・F(エフ)・G(ゲー)・A(アー)・H(ハー)・C(ツェー)】
という音が出ることになります。
実は、このC(ツェー)という音。
いわゆる「ドレミ」の「ド」の音と同じ音なのです。
つまり、グループ分けした4つのうち唯一、ドレミ読みと楽譜上の音が同じ音になるグループということになります。
C管楽器のみなさんは、チューニングの時に
「B♭(ベー)の音を出して」と言われたら「シ♭」の音を出せばOK
というふうに覚えておきましょう。
吹奏楽で基準音になりやすい「B♭」の音は、C管楽器では「シ♭」となるので、「ドレミファソラシド」と吹いた時には出てこない音になりますね。
吹奏楽ではどうしてもB♭で合わせるシーンが多いので、ちょっと覚えにくいかもしれませんが、「B♭(ベー)」=「シ♭」と覚えておくといいと思います。
ドレミ読みと音が同じ、ラッキーなグループ!→【実音楽器】といいます。
C管楽器担当のみなさんは
「自分の楽器のドは、ピアノやリコーダーのドとズレれているから、えっとえっと…」
などと考える必要は一切ありません!
ですので、難しいことは一切考えずにいきましょう!(笑)
このような、ドレミ読みと譜面上の音が同じ楽器のことを、実音楽器といいます。
(それに対して、①B♭管②F管③E♭管のように、ドレミ読みと譜面上の音が異なる楽器のことを移調楽器といいます。)
吹奏楽部に入って当初、私がドイツ音名とドレミの違いに苦労していたとき、フルートやオーボエはドレミと同じで良いのだと知った時は、
「フルート&オーボエ、めっちゃいいなぁ…なんか、ちょっとズルいよなぁ…」
なんて思っていたことを思い出します。。。(^_^;
まとめ

吹奏楽部員が、入部当初に混乱させられるポイントである、ドイツ音名。
また、先輩達がよく話している○○管という言葉。
これらについて、基礎的な内容をご紹介しましたが、いかがでしたか?
ドイツ音名という言葉だけ聞くと難しそうなイメージを持たれるかもしれませんが、初心者のみなさんは、このページで解説をした
①チューニングでB♭(ベー)の音を求められたら、何の音を出せばいいのか分かる
②自分の担当楽器の「ドレミファソラシド」を、ドイツ音名で言える
この2点が分かれば、十分合格点といえます。
この2つをクリアしてから少しずつ、ドレミファソラシドでは出てこない、♯や♭のつく音についてもドイツ音名で覚えていけると、とても良いですね♩
とは言っても、ドイツ音名は私の経験上、分からないまま言葉だけを無理に暗記するのではなく、日頃の基礎練習・曲練習で先生や先輩の話す言葉をよく聞くことで、自然と頭の中に入っていくことが多いです。
あ、この音は「A(エー)」になるのか~。
今日合わせたこの音は「E♭(エス)」か~。
という具合ですね。
いきなり全部の音のドイツ音名を覚える必要は、まったくありません^^
全部を覚えていなくても、日頃の練習にまったく支障は出ません^^
まずは、よく出てくるB♭(ベー)やCD(ツェー)からはじめてみてください♩
最後までお読みいただき、ありがとうございました。





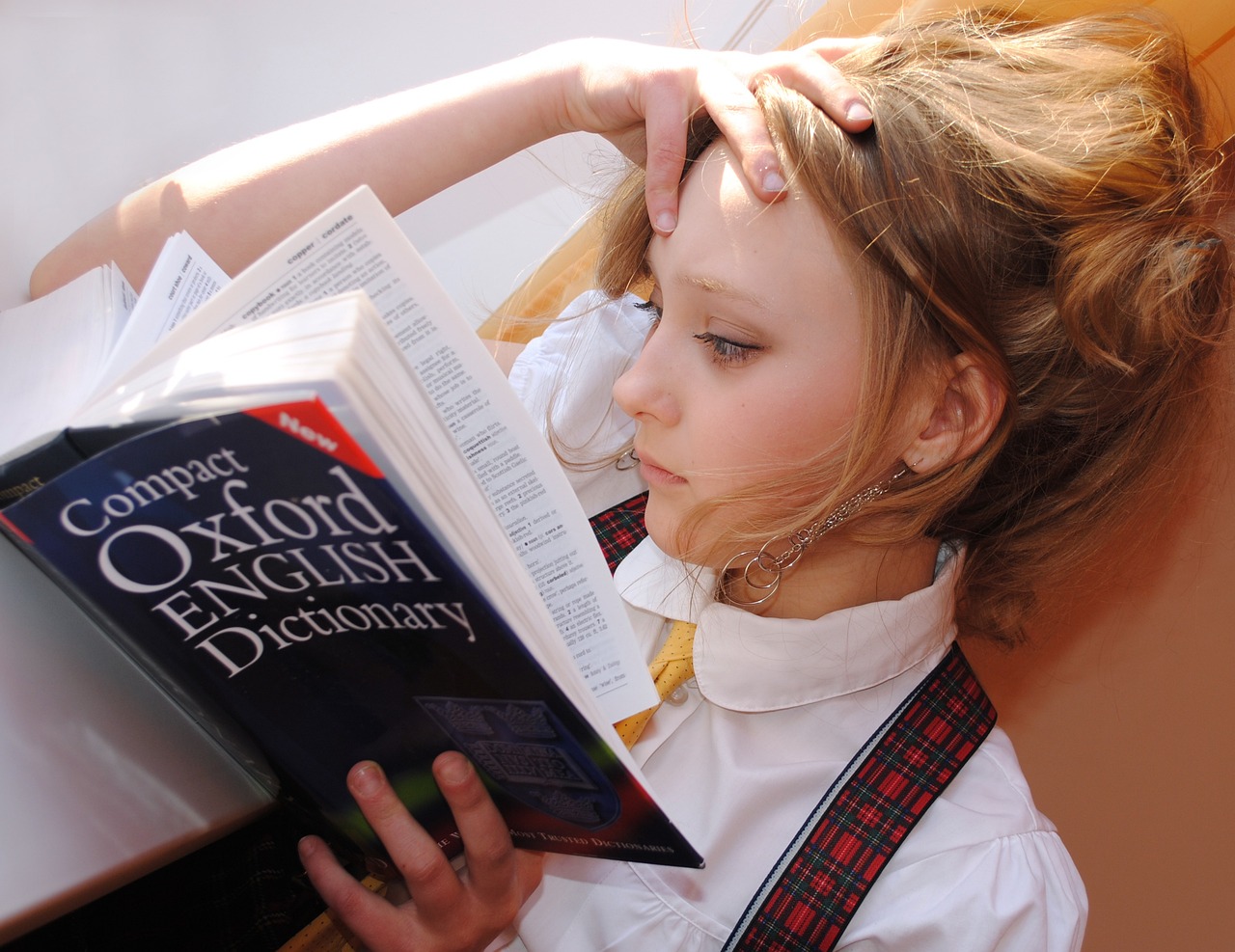

コメント